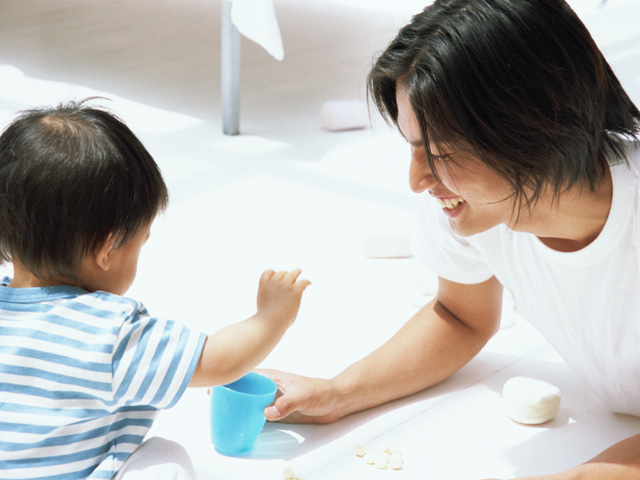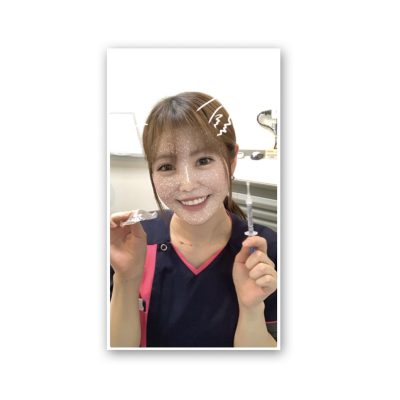「second Sunday in May」
新緑の色増すこの五月を迎えると必ず一つの英文が頭を過ります。〝second Sunday in May〟、「母の日」を指します。中学に入学して間もない、まだ学習意欲に燃えていた五月、英語の教科書に登場して来たセンテンスです。英語教師グレゴリー先生はカセットテープレコーダーに録音した英文を私たち生徒に聞かせ、繰り返し、繰り返し、教室の外まで響き渡るような大きな声で発音させました。中学から親元を離れ寮生活をしていた私にとって、その頃はまだ母が恋しくもあり、このセンテンスが特に印象に残ったのかもしれません。四十年たった今でもふと口ずさみます。
そして、〝second Sunday in May〟という言葉が頭を過(よ)ぎると同時に思い出す「母の日」のエピソードがあります。
昭和四十一年、私が小学校四年生の時のことです。友達の家の近くに小さな花屋さんがありました。母の日の二、三日前、通りすがりに花屋の店先を覗いてみると、赤とピンクのカーネーションがあふれんばかりにバケツに生けてありました。とても鮮やかでした。その時、素晴らしい計画が私の頭に浮かびあがりました。値段を見てみると一本十円、僕が持っているお金で二本買えます。「母の日」は日曜日で学校は休みですし、いつもより早く起きて、密かに家を抜け出し、赤とピンクのカーネーションを一本ずつ買って帰り、母が起き出して来たときにプレゼントとして渡し、母を喜ばそうと思ったのです。花屋のおばさんに日曜の朝は何時から店を開けるのか尋ねました。八時だそうです。
母の日の前の夜、寝床についてもドキドキしました。明日は、母にばれないように自力で早起きして、密かに家を出る必要があるからです。しかも、より母を喜ばそうと思って四歳になる弟も一緒に連れて行くことにしていたのです。
当日、ちゃんと目が覚めました。弟を起こし、「しーっ」と言いながら廊下を静かにあるき、玄関のドアをそーっと閉めて表に飛び出しました。二人で花屋に向かって駆け出します。母の笑顔を思い浮かべながら二人ともキャッキャと走ります。八時に花屋に着くと、もうお店が開いていました。一安心です。花屋のおばさんは暖かい眼差しを向け、僕らを労い、二本のカーネーションを綺麗に包装してくれました。
家に帰り着き、玄関のドアを息を殺して静かに開けました。すると上がりかまちに、母が寝巻き姿のまま立っているのです。間髪を入れず怒声が飛んできました。「どこさん、行っとったつね!」。鬼のような形相です。
出かけていた理由は伝えましたが、残念ながら、それでも怒声が止まりませんでした。朝早くから無断で小さな弟を連れ出した事がいかに母に心配をかけたか、いかに私が悪いことをしたかを言われ続けた気がします。そこからの記憶は曖昧ですが、「ありがとう」の言葉もなく、母の日の数日前から思い浮かべ、楽しみにしていた母の笑顔を全く見ることができなかったことだけは覚えています。
母が亡くなって、十四年が経ちます。葬儀の日、私の目に涙はありませんでした。私の母は小学校の教員でした。今でも私が感じるのは、母は私よりも世間体の方が大事だったのだろうということです。愛されて育った感じはしません。
先月、文章教室に初参加した私は、講師の小林先生の「悲しみを読む、悲しみを書く」という作品の中で森進一が歌った「襟裳岬」の歌詞についてのくだりにいたく感銘を受けました。第二回目の授業中は、皆さんの作品を聞いているとき、「北の街ではもう・・・」という歌が頭の中でなりっぱなしだったほどです。
私はこの二十余年、常々、前述の母のエピソードを病院のスタッフに言って聞かせ、「こういう子供の気持ちを大事にしない母親にはなったらだめだぞ」と、説教をしてきました。自分ではスタッフのために話をして来たつもりでいましたが、実は、小林先生がおっしゃった「表現するということは、心の底の暗闇に言葉の糸を下ろして、『悲しみ』をすくい上げる営みである」をしていたのかもしれません。
こうやってこの文章を書いてくると、予想もしていなかったことですが、「悲しみを暖炉でもやしはじめて・・・・暖めあおう」という歌詞の通り心が温まってきた自分を感じています。外の景色に新緑を感じ、あと二日で今年の母の日を迎える今、ふと、空に向かって一つの言葉を言ってみたくなりました。
「おかあちゃん、生んでくれたことはありがとう」